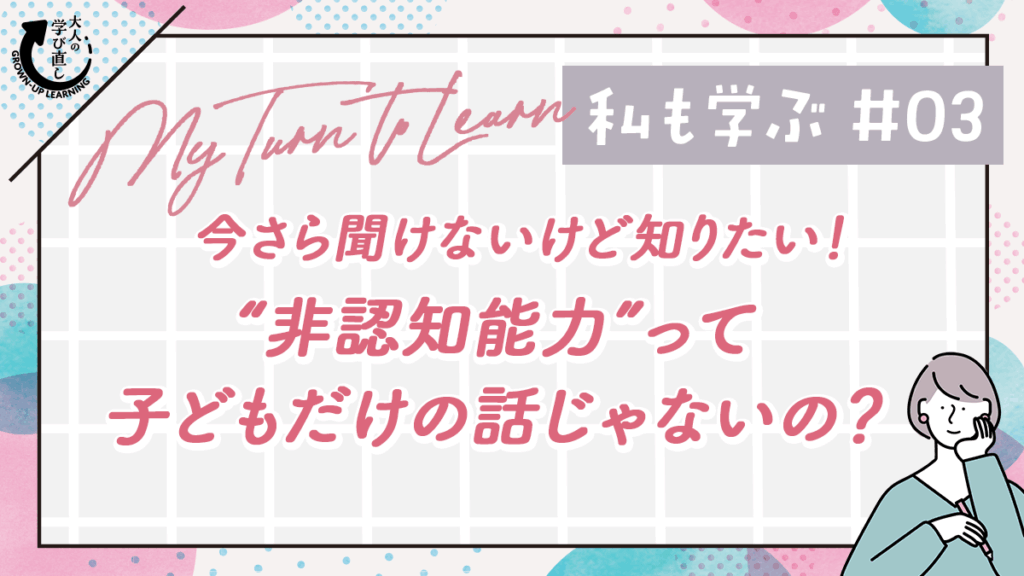
今さら聞けないけど知りたい!
“非認知能力”って子どもだけの話じゃないの?

「最近よく聞く“非認知能力”って、何なの?」
「子どもには大事らしいけど、大人には関係ないよね?」
そんなふうに思っていませんか?
学校説明会などで耳にして気になってはいるが、はっきりとはわからないままになっている方も多いかもしれません。
この“非認知能力”という言葉は、子どもだけでなく、私たち大人にも深く関係している概念です。
今回は、「非認知能力ってなに?」「なぜ大人にも必要なの?」「どうすれば育てられるの?」という素朴な疑問に、やさしくお答えしていきます。
非認知能力とは?
非認知能力とは、かんたんに言うと「テストの点では測れない力」のことです。たとえば、やる気、集中力、自信、我慢する力、人とうまくつき合う力、考え続ける粘り強さなど、社会に出てからも必要とされる力です。
これに対して、計算、漢字、英単語など、明確に点数で測ることができる知識やスキルは「認知能力」と呼ばれます。
「認知能力」も「非認知能力」もどちらも大切な力ですが、最近では「非認知能力こそが、その後の学力や人生の充実度に強く関係している」という研究が世界中で増えてきました。

マシュマロテスト
とくに注目されたのは、アメリカのスタンフォード大学で行われた「マシュマロテスト」の研究です。
4歳の子どもに「マシュマロを今すぐ食べるか、15分待てばもう1つもらえるか」という選択をしてもらいました。
その後の追跡調査から、15分待つことができた子どもは、のちの学業成績や社会性が高かったという結果が出ました。
このように、目先の欲求をコントロールする力や、やり抜く力、すなわち「非認知能力」が人生に大きな影響を与えることが明らかになってきたのです。
「非認知能力」は大人には関係ない?
では、この「非認知能力」は大人には関係ないのでしょうか?
そんなことはありません。むしろ、子どもを育てる立場にある私たちこそが、“自分の非認知能力”を育てることが、家庭や仕事、そして自分自身の幸福感に大きく影響するのです。
たとえば、育児、家事、自身の仕事に追われてついイライラしてしまうことがあります。しかし、「自分の気持ちを言葉で整理してみる」「今日はあえて完璧を目指さない」といった小さな意識の持ち方が、自分の感情のコントロール力(自己制御力)を高めます。
あるいは、子どもに「もっと頑張りなさい」と言いたくなったときに、まずは「どうしたらやる気が出るかな?」と一緒に考える。これも「共感力」や「対人関係スキル」という非認知能力を、親自身が使っている瞬間です。
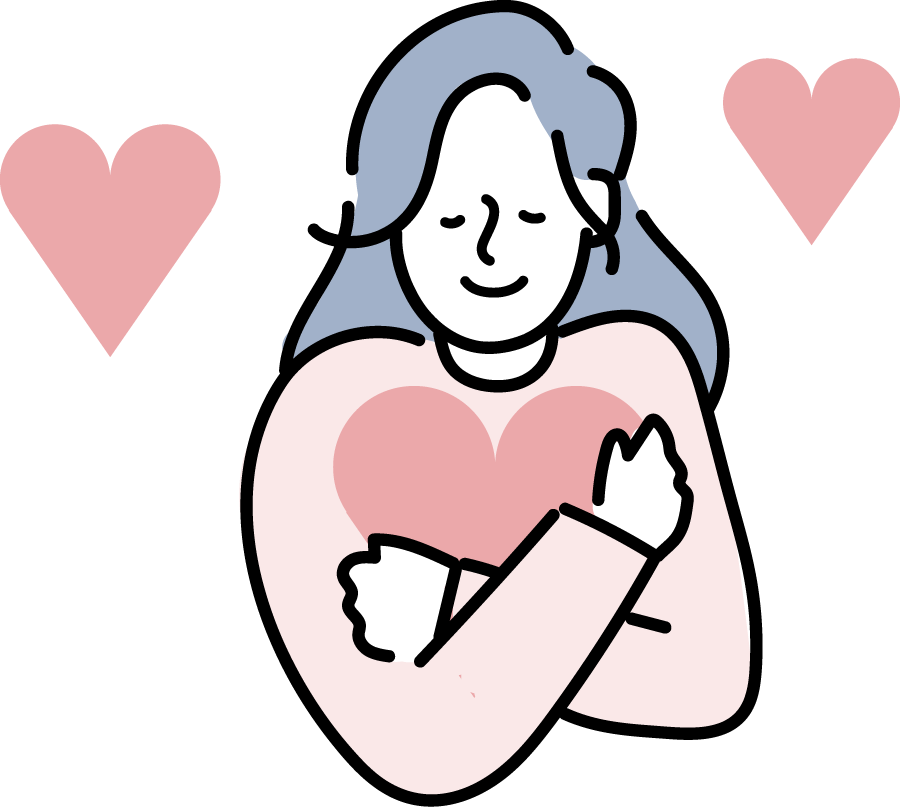

非認知能力は、特別な訓練をしないと育たないものではありません。実は、毎日の生活の中に「育てるチャンス」がたくさんあります。朝起きて予定通りに動けたとき、ちょっとした失敗から立ち直ったとき、誰かの話を最後まで聞けたとき、そんな日常の積み重ねが、子どもにとっても、私たち大人にとっても、“生きる力”につながります。
自分自身を信じて行動すること、失敗してもまた立ち上がること、人との関係を大切にすることなどは、すべて見えない力であり、たしかに大切な力です。そしてその力は、子どもも大人も、今日から少しずつ育んでいけるものなのです。学び、成長し続ける大人の背中こそが子どもにとって最高の教科書になるはずです。
