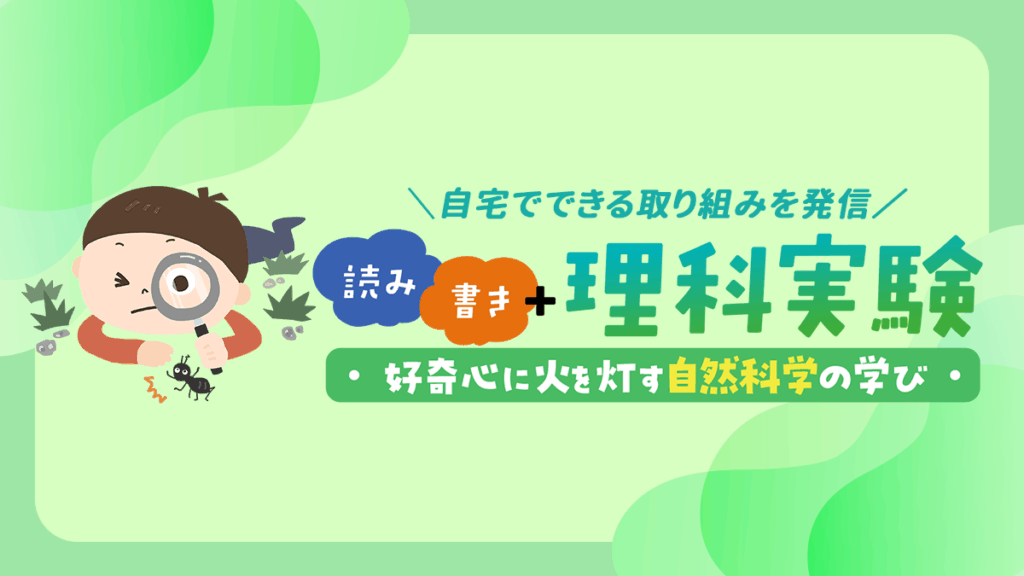
読み、書き、“理科実験”
─好奇心に火を灯す自然科学の学び―
理科実験は、五感をフルに使って学ぶことができる学び方
理科実験は、五感をフルに使って学ぶことができる学び方です。目で見て、手で触れ、鼻でにおいをかぎ、また、現象の変化を観察することができます。そこには驚き、疑問、仮説と検証の連続であり、子どもの好奇心に火を灯す本来のあるべき“学び”のエッセンスが詰まっています。

かつて、2000年代初頭には、学習塾等で「理科実験教室」がブームとなりました。ペットボトルロケット、結晶づくり、酸とアルカリの実験…など、科学の魅力を体験する場として、多くの子どもたちが目を輝かせて学んでいました。
しかし、最近では理科実験を主軸に据えた教室は激減しています。理由は明確です。指導者の準備負担が大きく、必要な道具や安全管理など、コストとリスクが高いことが挙げられます。経営の効率化が求められる民間教育機関において、体験型教育が敬遠されるのはある意味、必然だったのかもしれません。
ICT端末の普及に伴う教育のデジタル化が進む中、好奇心をベースにした本質的な学びの意義を再確認したいのです。子どもが、「なぜ?」「どうなるの?」と問いを持ち、自分の手で確かめる──この経験は、「理科」という教科にとどまらず、生きる力、思考力、探究心そのものを育みます。
教科を超えた学びの“根っこ”として、理科実験は今の子どもたちにこそ必要な体験だと考えます。
「自然科学」(ナチュラルサイエンス)の一環
「理科」「理科実験」という狭い枠で論を展開する前に、これらは「自然科学」(ナチュラルサイエンス)の一環であるということを理解しなければなりません。「自然科学」(ナチュラルサイエンス)とは、自然現象を対象として取り扱い、そのうちに見いだされる普遍的な法則性を探究する学問のことです。一般的には、便宜的に「物理」「化学」「生物」「地学」と分けていますが、科学的なアプローチで理解を図るという学びなのです。
太古の時代から「自然」の恵みを受け、怖れ、ヒトは共存してきました。「自然科学」の研究が進むにつれ、現代の私たちはある程度の予測のもと日々を安心して過ごすことができています。しかし、まだまだ解明につながらない災害などの分野においては、その恐怖をシミュレーションしながらいかにその危険から身を守るかという点でニュースやメディアなどで呼びかけがされています。
世界的にSTEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematicsの5つの領域を統合した教育)への関心が高まる中、保護者が子どもの学びに関与する機会が増えています。理科実験は、家庭内でのコミュニケーションにおいても非常に相性のよい活動です。
例えば、卵が浮く水の濃度を調べる「食塩水の実験」など、キッチンの材料で楽しめる実験も豊富にあります。準備も後片付けもシンプルにできるように設計すれば、子どもにとっても保護者にとってもハードルはぐっと下がります。「理科実験」という言葉を使うまでもなく「料理」を通して、科学的の芽を育むことができます。

また、「自然科学」の観点から、野外での体験活動をお勧めします。自然の中でこそ子どもの好奇心は育まれます。自然そのものが教材です。同じ場所でも季節によってその景色は大きく変わります。そこにある植物、生物、気候などを観察することが好奇心を育む第一歩なのです。
高校入試で良く出題される「木炭を燃焼させるとどうなるか説明しなさい。」という記述問題があります。型通りに暗記して「炎を出さずに赤くなって燃える。」というのも一つではありますが、できるなら、子どものときに飯盒炊飯やバーベキューをする時に木炭を燃焼させる経験を積んでいれば、うちわを必死に仰いで酸素を送り込み木炭が赤くなったことを鮮明に想起することができるでしょう。

私たちActive!の「科学探究」というコーナーを通して、自宅でできる取り組みなどを発信しています。このようなネタも活用していただきながら、皆様と共に子どもの好奇心の火を灯していきたいと考えています。学びの本来あるべき姿を身近なところから見直し、学習の基礎を「読み」「書き」と並列で「理科実験」を並べ、「自然を科学する力」の育成に励んでまいります。
