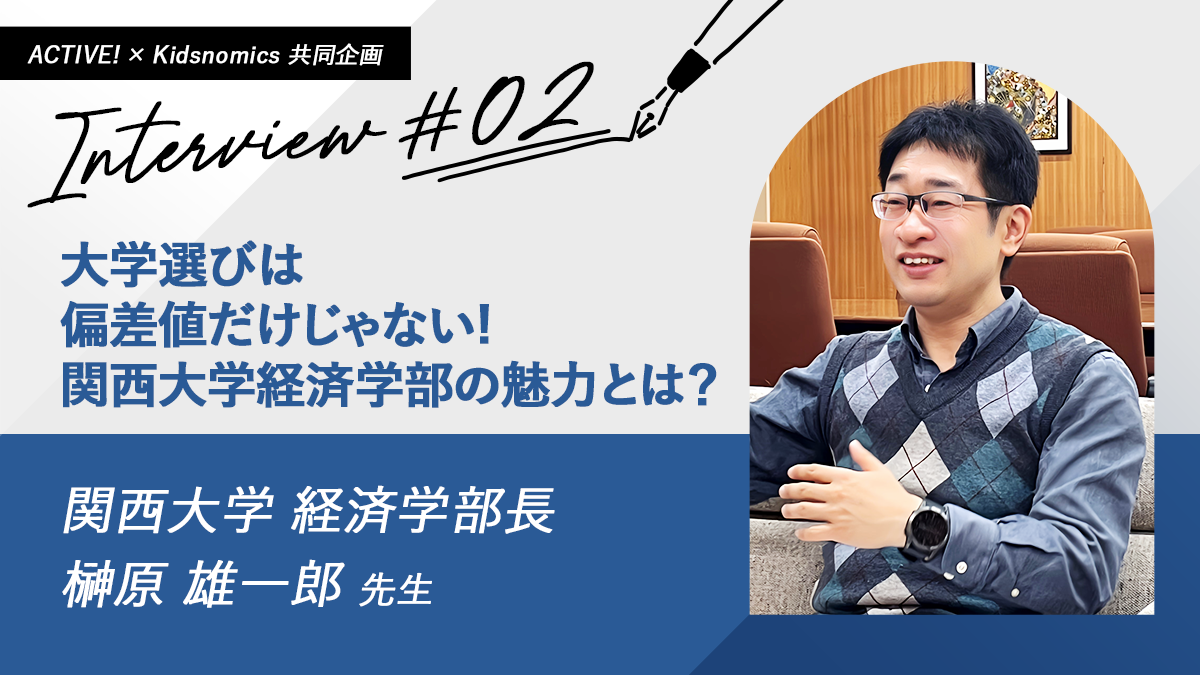大学の経済・経営学部を探検!
関西大学 経済学部長
榊原 雄一郎先生【第5部】
教育情報メディア「ACTIVE!」x 社会経済ニュースメディア「キッズノミクス」共同企画
※第1部~第4部は
こども経済メディア キッズノミクス に掲載しています。
はじめに
こどもと一緒に楽習する教育情報メディア「ACTIVE!」と社会・経済ニュースメディア「キッズノミクス」では、「好奇心を刺激する学び」をテーマに記事の配信に取り組んでいます。
今回は両メディアの共同企画「大学の経済・経営学部を探検!」と題した特集記事をお届けします。

今回は、関西大学経済学部の榊原教授をお迎えし、経済学部の学びの魅力やカリキュラムの特色についてお話を伺いました。
地域経済論を専門とする榊原教授に、都市の発展や経済構造の違いを通じて「広い視野で社会を理解すること」の大切さを教えていただきました。また、関西大学ならではの教育環境やゼミでの学び、学生たちの就職先の動向についても触れ、現代の学生が持つ課題や未来の可能性についてもお伺いしています。
進路選びに悩む学生やその保護者の皆さんにぜひ読んでいただきたいインタビューです。
インタビューにご協力いただいた先生
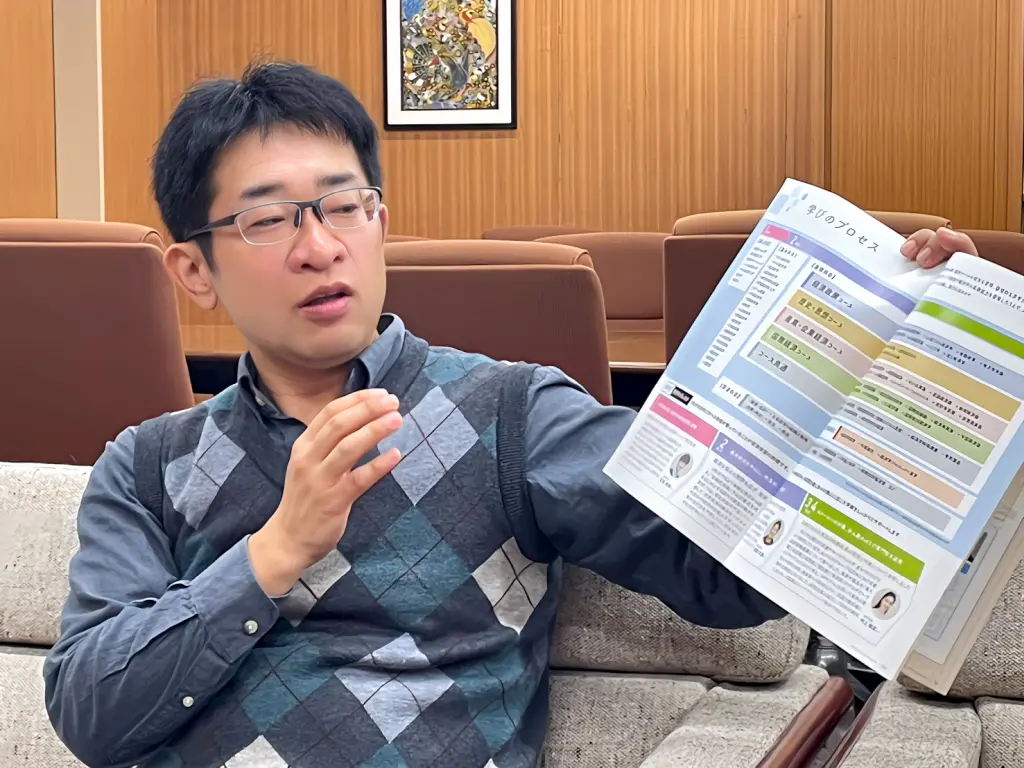
榊原 雄一郎 先生
関西大学
経済学部 学部長
地域経済論を専門とし、都市の発展や産業集積に関する研究に取り組む。東北大学で経済学を学び、関西大学にて長年教育・研究活動を行い、地域経済の視点から日本各地の都市や産業の動向を探求。学生に経済の面白さを伝え、広い視野を持った社会理解を促す教育に力を注いでいる。
保護者様へのメッセージ

小学生、中学生、高校生には社会や経済に「興味を持ってほしい」という思いがあります。
大人がどのような関わり方をすればよいのか、何をすると良いのか、アドバイスをお願いします。
榊原先生:そうですね、自分の好きな情報ばかりを追わないことが重要だと思います。

それは、わかりやすいですね。
榊原先生:はい。世の中にはさまざまな動きがあって、AIも非常に進化していますよね。私もYouTubeをよく見ますが、一度何かを視聴すると、どんどんそれに関連する動画がおすすめされてきます。例えば、私は洋楽が好きで、3曲ほど聞くとその後も「こんな曲もおすすめです」という感じで、次々に流れてくるのです。精度が高くて便利なのですが、その反面、自分の好きな音楽の幅が狭くなってしまうというデメリットも感じます。
ですから、情報化社会と言いながらも、実は情報弱者を生み出している面もあります。好きなものを楽しむのは大前提ですが、それ以外のところにもアンテナを張ることが非常に重要だと思っています。
自分が見ている世界が全てではないので、なるべく広く物事を見てもらいたいと強く感じています。そういった視点を持つことを大切にしつつ、それ以外の視点も広げてもらいたいと思っています。

子ども自身では気がつかないこともあると思いますので、保護者様が一緒に見るというのも1つの方法でしょうか。
榊原先生:そうですね。うちの子どもの話をするのは少し恥ずかしいですが、今はテレビの取り合いをしています。子どもが2人いるのですが、どのYouTube番組を見るかで取り合っています。
昔は親や子どもが一緒にテレビを見ていたことが多かったですね。私がプロ野球を好きになったのは、親が好きで一緒に見ていたからです。おじいちゃん、おばあちゃんと大相撲を見ていた時期もありました。ニュースも家でつけっぱなしにしていたので、自然と耳に入ってくるという感じでした。
しかし今のうちの子どもの場合、自分が見たいものしか見ないのです。兄弟姉妹でさえ一緒に同じ番組を楽しむという発想があまりないですよね。例えば、お姉ちゃんが30分見ていると、下の子が「お姉ちゃんずるい」と言って文句を言います。一緒に何かを楽しむことが少なくなっています。
大学生でもニュースに対してアンテナが低い子が多いと感じています。彼らがニュースに触れる機会が少ないのかなと思います。
親がニュースに興味を持っている環境があれば、こうした状況もだいぶ変わるのではないかと感じますね。

高校生に「まず学部を調べてみて選びなさい」と伝えることが多いのですが、それが本当に正しいアドバイスかどうかをお伺いさせてください。
学部を見る際、ホームページやパンフレットでどういった点を見れば良いのか、学生たちは悩むことが多いのです。
たとえば、経済学部を目指す場合、いろいろな大学がありますが、どこを基準に調べると良いのでしょうか。
榊原先生:それは非常に難しい問題ですね。ただ、パンフレットから読み取れる情報にはそれほど大きな違いはないことが多いです。
実際、パンフレットで説明しても、どの大学も似たような内容になってしまう部分はあります。強いて言えば、カリキュラムの内容に差があるかもしれませんが、それよりも「生の学生の声」を聞くことが非常に重要だと思います。
たとえば高校でも、入学時の偏差値と卒業時の進学先は必ずしも一致しないですよね。

ええ、そのとおりですね。
榊原先生:入学時に学力が高くても卒業時の学力が高くないケースもあれば、逆に大きな成果を出す学校もありますよね。関西大学経済学部では、ゼミをはじめ教育について非常に熱心にそして丁寧に取り組んでいるため、卒業生の満足度は非常に高いです。また、就職先についても、就職率が高いということだけではなく学生たちが自分の希望する企業に就職できるケースが多いです。
そういった学生の声を聞く機会、たとえばオープンキャンパスなどに足を運んでいただけると非常にありがたいですね。遠方でなかなか来づらい場合もあるかと思いますが、それでも可能であればぜひ来てほしいです。
また、ゼミ選考なども主に紙ベースで行っていますが、最近ではインスタグラムなどを活用して、学生たちの日々の様子を発信しています。こういった情報を通じて「自分もこんな風になりたい」と思えたら、その大学が最良の選択肢になるのではないかと思います。

私は国公立大学の出身ですが、私立大学に来て、その良さをたくさん学ぶことができました。キャンパスの活気や課外活動など、全体を通じた学びが非常に素晴らしいと感じます。関西大学にもぜひ足を運んで、その熱気や生き生きとした学生たちの姿を見ていただきたいですね。これからも、先輩たちの生の声を可能な限り発信していくつもりです。
経済学部ホームページでは学部内の各種イベントや日々のひとコマを発信しています。更新頻度も高く、見るたびに違う記事が上がっていると思いますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。
関西大学経済学部ホームページを見た上でぜひオープンキャンパスにも来ていただければと思います。

冒頭で話された、数学、社会を選択する入試制度について、実際にはどちらの科目で入学してくる学生が多いのでしょうか?
榊原先生:経済学部の試験に関して、数学か社会かどちらの科目で合格してくる学生が多いか、一概には言えないところがありますね。
ただ、経済学部の授業では必ず「数学の洗礼」を受けるようなカリキュラムが組まれています。つまり、数学を避けて通ることはできないのです。
ミクロ経済学入門やマクロ経済学入門ではすべての内容で数学を使うわけではありませんが、それでも数学の知識は非常に重要です。また、「経済ツール」という科目もあり、経済学で必要となる最低限の数学をわかりやすく教えています。
ですから、経済学部ではどうしても数学を学ばなければならない状況であり、それが学生の苦手意識の一因になっているかもしれません。 関西大学経済学部では、その苦手意識を取り除くためのカリキュラムを準備しています。

なるほど。授業ではやはり数学を使うのですね。
榊原先生:そうですね。ちなみに私の授業ではあまり数学は使っていないのですが、下位年次では数学を学ぶことが必須になっています。これは、いわゆるロジカルシンキング、つまり論理的に考えるためには、数学的な思考が間違いなく重要だからです。
また、社会を理解する上でデータや数値を見ることも重要です。例えば、私は学生にこんな質問をすることがあります。「ソニーって何の会社だと思う?」と学生が企業研究をしている中で、そういう話をすることがあるのですが、多くの学生は「テレビの会社」と答えます。
しかし、ソニーの決算書を見ればわかるように、テレビ事業は実際にはそれほど大きな収益を上げていないですよね。ゲーム事業は想像しやすいかもしれませんが、金融やコンテンツやイメージセンサーがどれくらい収益を上げているのかをちゃんと数字で把握することが重要なのです。
社会を理解するには、「なんとなく」だとかイメージで済ませるのではなく、しっかりと根拠に基づいた考えを持つ必要があります。特に経済学部の学生には、データを基に考える力が求められています。また、こうした力を身に付ければ、企業側からも経済学部の学生に対して魅力を感じてもらえるのではないでしょうか。
数学的な思考ができ、データや数値に強い学生を育成することは経済学部の魅力向上につながると考えています。

ありがとうございます!非常にわかりやすいです。
榊原先生:はい、学部長としても非常に悩ましいところではありますが、これからも学生たちにしっかりとこの重要性を伝えていきたいと思っています。

本日はたくさんのお時間をいただき、ご丁寧なご説明を本当にありがとうございました。
榊原先生:こちらこそ、ありがとうございます。ぜひ若い世代に経済の面白さを伝えていただけたらと思います。
最初は経済学や数学に対して苦手意識があるかもしれませんが、経済学部に入れば学べることはたくさんありますので、ぜひ楽しんでほしいと思います。

あとがき
今回のインタビューでは、関西大学経済学部の学部長から、学部の魅力や学生たちの学びに対する情熱、そして地域経済論を通じて見る現代都市の変化について、さまざまな視点を伺うことができました。経済学というと難しいイメージを持たれることが多いですが、関西大学では、学生が実践的なスキルを身につけ、社会の多様な課題に対応できるようなカリキュラムが整備されています。特にデータ分析や地域経済の視点を重視した授業は、これからの時代に欠かせない力を育むでしょう。
また、学生一人ひとりが自分の興味やキャリアに合った科目を選択できる柔軟なカリキュラムがあり、ゼミやプロジェクトを通じて主体的に学ぶ環境が整っています。これにより、大学生活を通じて「何を学び、どう活かすか」を深く考える機会が与えられます。
教授が語る「自分の視野を広げ、根拠に基づいた考えを持つこと」の重要性は、これからの社会で生き抜くための大切な指針だと痛感しました。未来を担う若者が、ここで学び、社会で活躍する姿を思い描くことができるお話を聞かせていただきました。
榊原教授、お忙しい時間を縫って学びのあるお話をしていただき、ありがとうございました。
関西大学 経済学部長
榊原 雄一郎 先生 インタビュー
※第1部~第4部は
こども経済メディア キッズノミクス に掲載しています。