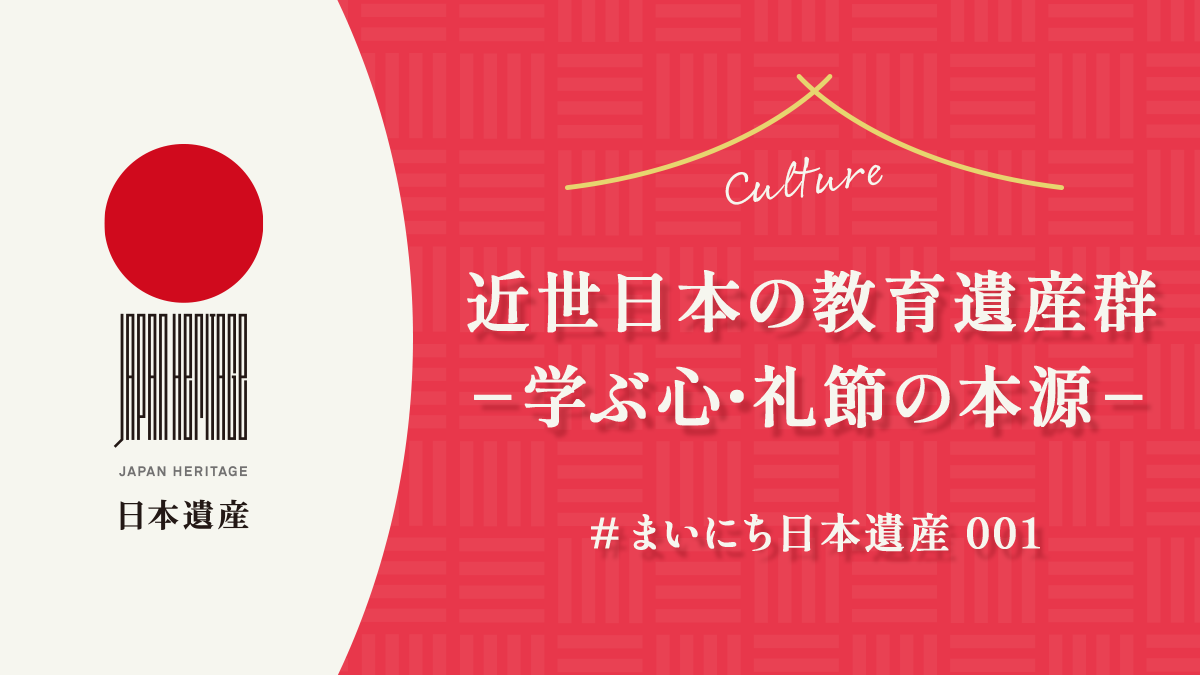
【#まいにち日本遺産 001】近世日本の教育遺産群ー学ぶ心・礼節の本源ー
江戸時代から続く日本人の礼儀の秘密とは!?
江戸時代から続く日本人の礼儀の秘密!
(動画ナレーションより)
日本には階級に関係なく教育を受ける文化がありました。
そんな日本の教育における伝統を今でも感じることができるのが足利学校、閑谷学校、咸宜園、弘道館といった教育遺産群。
江戸から近代日本へと受け継がれる学問発祥の地を調査してきたのでレッツゴー!
この歴史を感じる建物は旧弘道館。
近代教育制度導入前に教育の中心的役割を果たした藩校の1つで、日本最大規模なんだって!水戸藩の藩士やその子弟に対して儒学、算術、礼儀作法などを教えていました。
生徒たちが学びの間に休憩を取ったのがこの場所と言われています。すごく綺麗!
ここ偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園と並ぶ日本三名園の1つなんです!
徳川斉昭が園内に学問を象徴する梅を植栽したことで有名で、現代にも伝統が引き継がれています。
学問に励む人々にとっては体力も大切。
こんにちスタミナ食として広く愛されているウギですが、うなぎ好きの水戸藩の奉行が、うなぎが冷めないようにご飯の上に乗せたものを考案し、芝居小屋でも売り始めたのが鰻丼の由来という説があります。
昔の若き藩士たちも食べたかもしれないですね!
礼節を重んじる日本人の国民性の原点を知ることができました。
