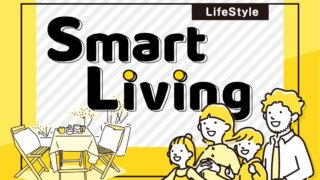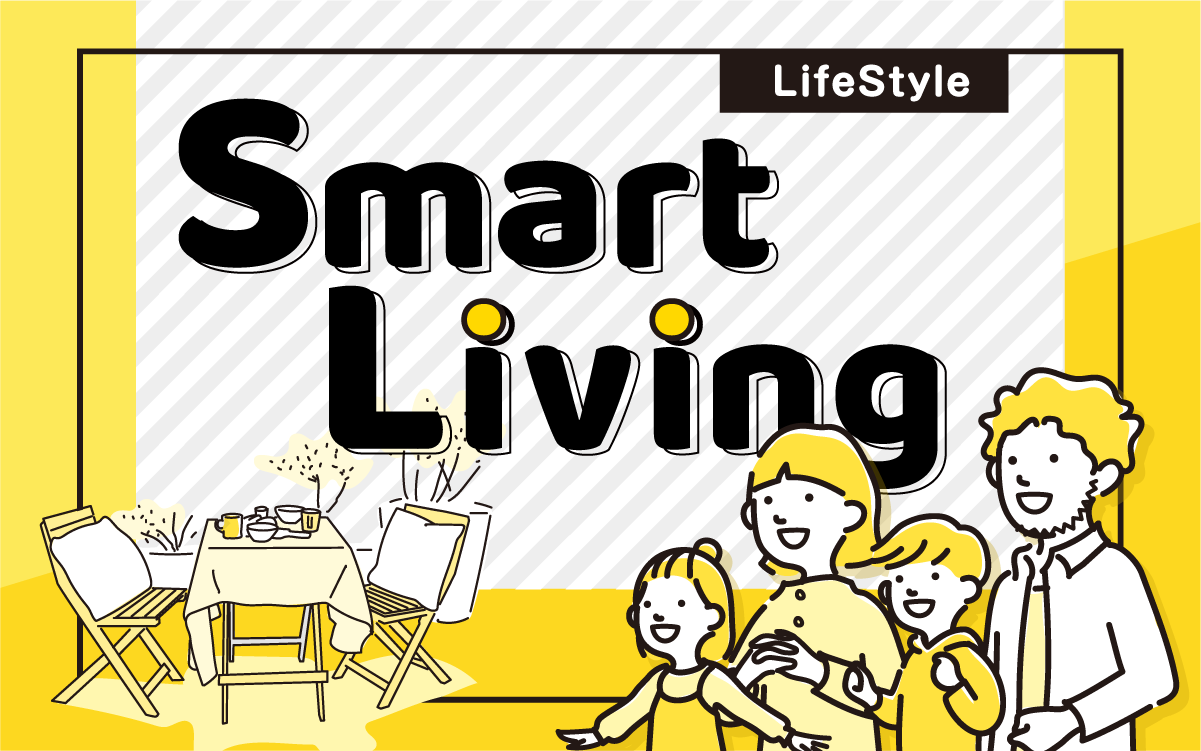
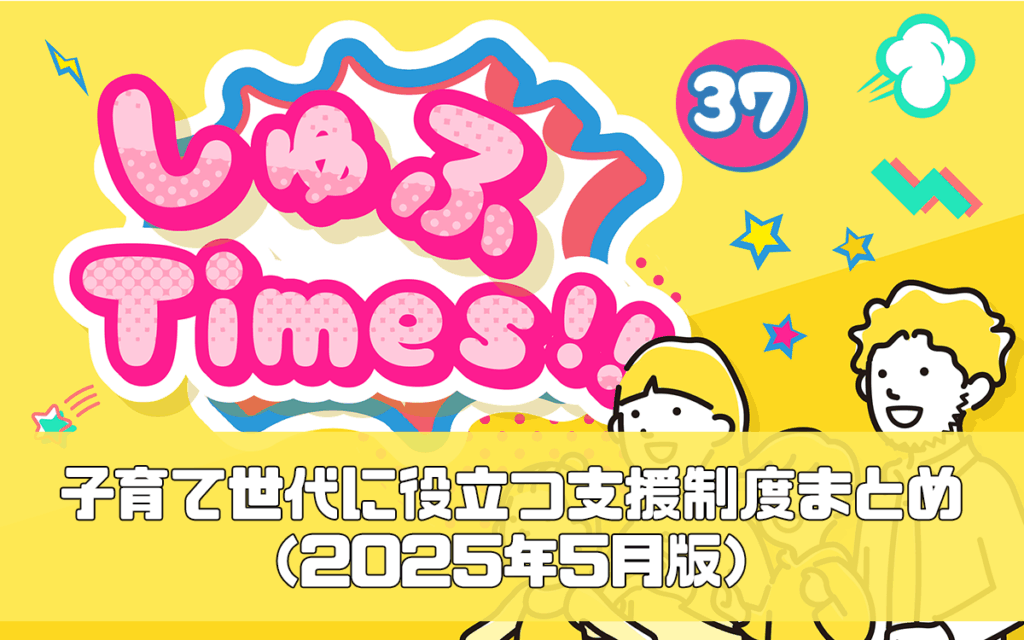
子育て世代に役立つ支援制度まとめ
2025年は子育て世代にとって大きな変化の年です。児童手当の拡充や新たな給付金、柔軟な働き方を後押しする制度など、生活や家計をサポートする制度が続々とスタートしています。最新の子育て支援制度を紹介します。

1. 児童手当の拡充で家計を強力サポート
- 支給対象が高校生年代まで拡大
- 2024年10月分(12月支給)から、児童手当の対象が「18歳到達後最初の3月末まで」拡大されました。
- 高校生年代のこどもがいる家庭も手当の対象となります。
- 第3子以降は月額3万円に増額
- 第3子以降は15,000円から30,000円に増額。
- 経済的負担が軽減され、多子世帯への支援が強化されました。
- 所得制限が撤廃
- 高所得世帯も対象になり、より多くの家庭が手当を受け取れるようになります。
- 申請・確認のポイント
- 高校生相当のこどもがいる家庭や多子世帯は、追加申請や自治体への確認が必要な場合も。自治体の案内をこまめに確認しましょう。
2. 出生後休業支援給付金で育児休業が取りやすく
- 2025年4月から新制度がスタート
- 両親が14日以上育児休業を取得すれば、最大28日間、休業前賃金の80%(手取り換算で10割)が支給されます。
- 共働き家庭の支援強化
- 経済的な不安が軽減され、育児休業を取得しやすい環境に。
- 申請方法と注意点
- 申請は勤務先の人事部またはハローワークで。書類の提出期限に注意しましょう。
3.「こども誰でも通園制度」で柔軟な保育利用が可能に
- 2025年4月から一部自治体で開始
- 0歳6か月~3歳未満のこどもが、就労要件にかかわらず、時間単位で保育サービスを利用できます。
- 短時間預けも可能
- 保育園に通っていないこどもも、必要なときに預けられます。
- 実施自治体の確認が重要
- 全自治体での導入ではないため、お住まいの自治体のホームページを確認しましょう。
4. 非課税世帯向け給付金・電気ガス代補助で生活防衛
- 住民税非課税世帯に特別給付金
- 世帯に3万円、こども1人につき2万円の加算支給が行われます。
- 電気・ガス代補助の再開
- 高騰する光熱費への対応として、家計支援策が講じられています。
- 申請の流れ
- 自治体から送られる案内に従い申請します。申請期限に注意しましょう。

5. 育児・介護休業法の改正で働き方がもっと自由に
- 3歳~小学校入学前のこどもを持つ親に柔軟な勤務制度を義務化
- 企業には、時短勤務や在宅勤務など、2種類以上の働き方を提供する義務があります。
- 残業免除制度の拡大
- 小学校入学前のこどもを持つ親も、残業免除の対象になります。
- 学校行事でも看護休暇が取得可能に
- 小学3年生までのこどもを持つ親は、入園式や卒業式なども休暇の対象となります。

6. 税制改正で「103万円の壁」を解消
- 課税最低限の引き上げ
- 2025年度の税制改正により、基礎控除と給与所得控除の合計が123万円に。
- 働き方に柔軟性
- 「103万円の壁」にとらわれずに働きやすくなり、家計の見通しが立てやすくなります。
7. 生命保険料控除の拡充(2026年分から適用)
- 扶養親族が23歳未満の家庭に朗報
- 控除限度額が4万円から6万円に増額され、税負担の軽減に寄与。
- 保険の見直しタイミング
- このタイミングでの見直しや契約変更を検討する家庭が増えそうです。
8. 省エネ住宅補助金で住まいの質もアップ
- 新築・リフォームで最大160万円補助
- 子育て世帯を含め、幅広い世帯が補助金の対象です。
- 家計と環境にやさしい住宅
- 光熱費削減や快適な住まいの実現につながります。
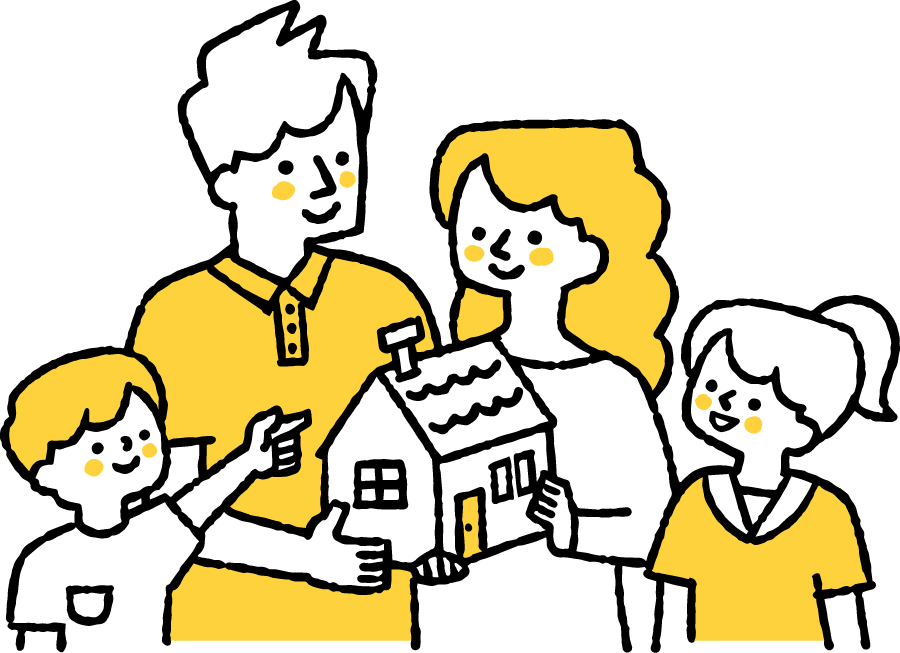
まとめ
2025年の子育て支援制度は、家計の負担軽減だけでなく、育児・働き方・教育など生活全般の質を向上させる内容が盛り込まれています。
- 制度ごとに対象や手続きが異なるため、必ず自治体や勤務先の公式情報を確認する
- 給付金や控除制度の申請期限を見逃さないようにする
- 家族のライフステージや収支計画にあわせて制度を柔軟に活用する
「知らなかった」ではもったいない内容ばかりです。最新情報を把握し、家庭に合った制度を活用することで、より安心・快適な子育てと生活設計を進めましょう。