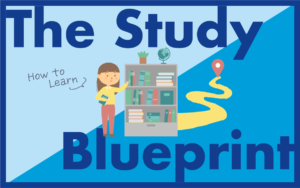第58回 切り替えと抑制|教育コラム “理論と実践”
学習にスムーズに取り組むことができない子どもたちが増えている 学習にスムーズに取り組むことができない子どもたちが増えていることが多くの教育関係者の関心事となっています。「子どもはそんなもんでしょ」という大人の解釈にも一理 […]
第57回 実物を見せると、読解力がつく|教育コラム “理論と実践”
実物を見せると、読解力がつく 「我が家はこうして読解力をつけました」(佐藤亮子著 くもん出版)には「実物を見せると、読解力がつく」という一節があります。同書では、読解力を「2Dの文章を3D映像に立ち上げる力である」と表現 […]
第56回 「音読+α」のひとくふう|教育コラム “理論と実践”
子どもたちの学習の基礎力を養ううえで「音読」はとても重要です。文部科学省は「すらすら読めること」が学習の前提である、と紹介しています。 音読をする文章の横に鉛筆でマルを5つ書いて、音読に取り組むごとに赤鉛筆で塗りつぶす、 […]
第55回 「お手本をうつす」こと|教育コラム “理論と実践”
『子どもが熱中する向山式漢字・言語指導法』(明治図書)には「お手本をうつすこと」ことは、すぐれた教育方法である、と書かれた箇所があります。学習の基本は「お手本をまねする」ということです。 習字でも絵でもお手本をまねします […]
第54回 思考とワーキングメモリ|教育コラム “理論と実践”
『教師の勝算』(東洋館出版社)に「思考はどう働くか」を解説している章があります。 「できる限り単純化した頭脳のモデル」として、・環境・ワーキングメモリ・長期記憶を以下のモデルで表しています。 「環境」とは見聞きするもの、 […]
第53回 語彙学習の2つの方法②|教育コラム “理論と実践”
『シリーズ国語授業づくり語彙』(監修:日本国語教育学会)には「語彙学習の方法論」として語彙学習の二つの方法が紹介されています。 「取り立て指導」と「取り上げ指導」です。 「取り立て指導」については、前回のコラムで取り上げ […]
第52回 語彙学習の2つの方法①|教育コラム “理論と実践”
『シリーズ国語授業づくり語彙』(監修:日本国語教育学会)には「語彙学習の方法論」として語彙学習の二つの方法が紹介されています。 「取り立て指導」と「取り上げ指導」です。 「取り立て指導」とは語彙としての特徴を学ぶ機会を独 […]
第51回 HSCへの理解を|教育コラム “理論と実践”
子真生会富山病院心療内科の明橋大二先生が書かれた「敏感さをもつ子どもたちHSCへの理解」を引用します。 「HSC」とは「High Sensitive Child」の頭文字を取った「ひと一倍敏感な子」を意味します。だいたい […]
第50回 耳栓をして音読|教育コラム “理論と実践”
子どもが学習をする際に「音読」は効果が非常に高いと言われています。学習は脳内で行われるため、脳を活性化させることは学習前および学習中の前提となります。その活性化において音読には大きな効果があります。 「音読」により脳の前 […]
第49回 算数のつまずき|教育コラム “理論と実践”
一般社団法人ワーキングメモリ教育推進協会が「算数のつまずき簡易チェック問題」を無料で公開しています。同協会代表理事の湯澤正通先生と理事の野瀨まなみ氏は次のように記しています。 「数や量を把握する認知システムに問題があると […]