日本語になった外来語たち#07:ランドセル/ Ransel
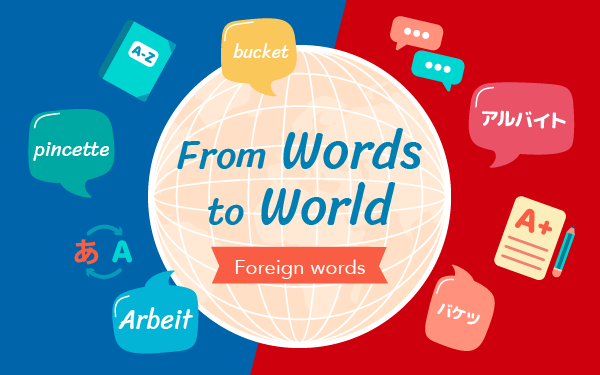
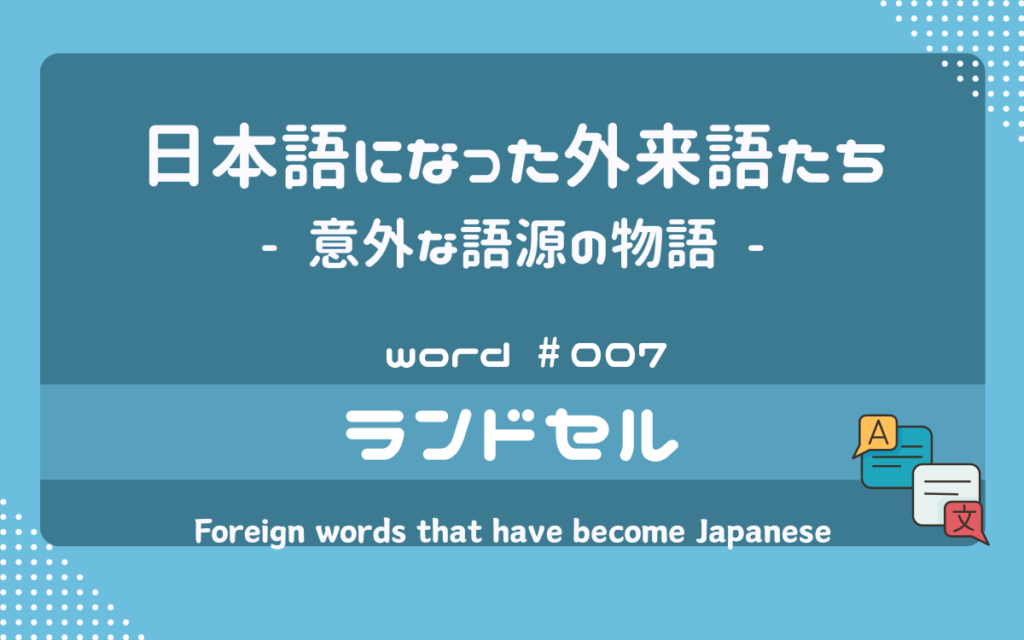
春になると、新一年生が背負うカラフルなランドセルが街をにぎやかに彩ります。でもこの「ランドセル」、もともとは日本の言葉ではなかったって知っていましたか? どこから来たのか、そしてなぜ日本の小学生の象徴となったのか、その背景を探ってみましょう。
語源
- 言葉:Ranzen(ランツェン) → Ransel(ランセル)
- もとの原語:オランダ語
- もとの意味:背負いかばん、軍用の背のう(※背のう:背中に背負う袋やリュックのこと)
- 日本語での使われ方:日本の小学生が使う、箱型の丈夫な通学かばん
日本語として使われるようになった背景
「ランドセル」という言葉は、江戸時代末期から明治時代初期にかけて、オランダから伝わった軍用の背のう「ransel(ランセル)」に由来します。明治時代、日本で学制改革が進み、学習院での教育にも軍隊式のかばんが取り入れられました。これが小学生の通学かばんに応用され、「ランドセル」と呼ばれるようになったのです。
最初は黒の革製が主流でしたが、昭和後期からは赤や青、近年ではパステルカラーや刺繍入りなど多様なデザインが登場し、個性を表すアイテムへと進化しています。

ちょっとした雑学
- ランドセルは日本独自の進化をとげた文化で、海外では「randoseru」とそのまま呼ばれ、注目されています。
- 最近では、海外のセレブや観光客が日本のランドセルをファッションアイテムとして購入するケースもあります。
- 軽くて丈夫な人工皮革(クラリーノなど)が主流となり、6年間安心して使える設計です。
- ランドセルの側面には防犯ブザーを取りつけるためのDカンがあり、安全面にも配慮されています。
- 卒業後にミニチュアランドセルとして再加工する「メモリアルランドセル」サービスも人気です。
親子で話してみませんか
「ランドセルって、実はもともとオランダ語が語源なんだよ。昔は“ランセル”って呼ばれる軍人さんの『背のう』、つまり背中に背負うかばんだったんだって。それが日本に伝わって、今の小学生が使うランドセルに進化したんだよ。君のランドセルには、どんなこだわりがある? 色や形、使いやすさってどう思う? 6年間の思い出がつまったランドセル、大事に使っていこうね!」

