日本語になった外来語たち#13:スイカ / Suika
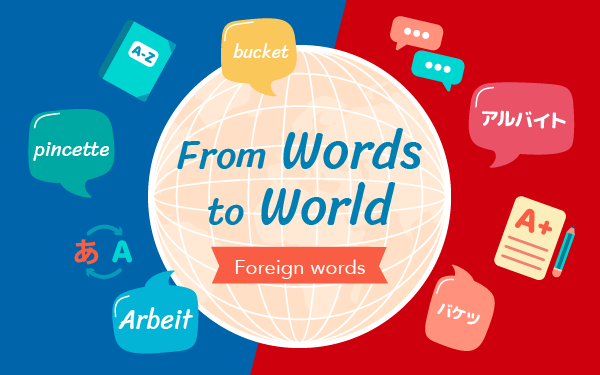
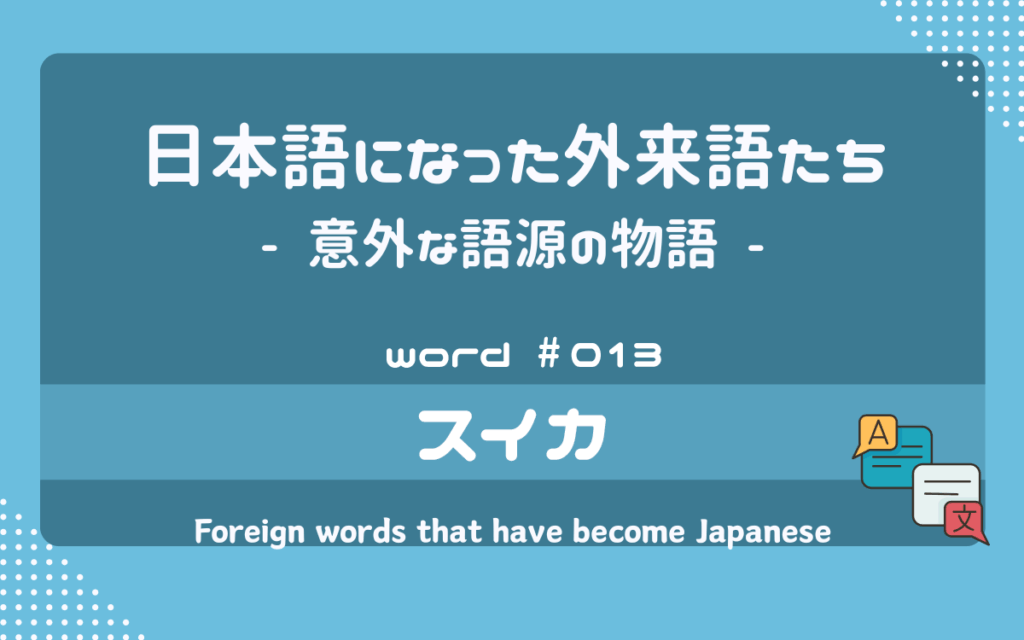
夏になると食べたくなる「スイカ」。冷たくて甘い、まさに夏の風物詩ですが、実はこの「スイカ」という言葉も外国語から来ているって知っていましたか?
今回は、スイカの言葉のルーツと日本への伝わり方について見ていきましょう。
語源
- 言葉:スイカ(suika)
- もとの原語:ポルトガル語「xīcā(シュイカ)」(もしくは、中国語経由の説あり)
- もとの意味:果物名(水分の多い瓜)
- 日本語での使われ方:夏の代表的な果物として、「スイカ割り」など行事にも使われる
日本語として使われるようになった背景
スイカはアフリカ原産で、古代エジプトでも食べられていたと言われています。日本には16世紀ごろ、中国やポルトガルの交易を通じて伝わってきたと考えられています。
当初は「水瓜(すいか)」や「西瓜(せいか)」などと書かれましたが、「スイカ」という読みはポルトガル語や中国語の発音に由来する可能性があるとされています。江戸時代にはすでに夏の風物詩として人気がありました。
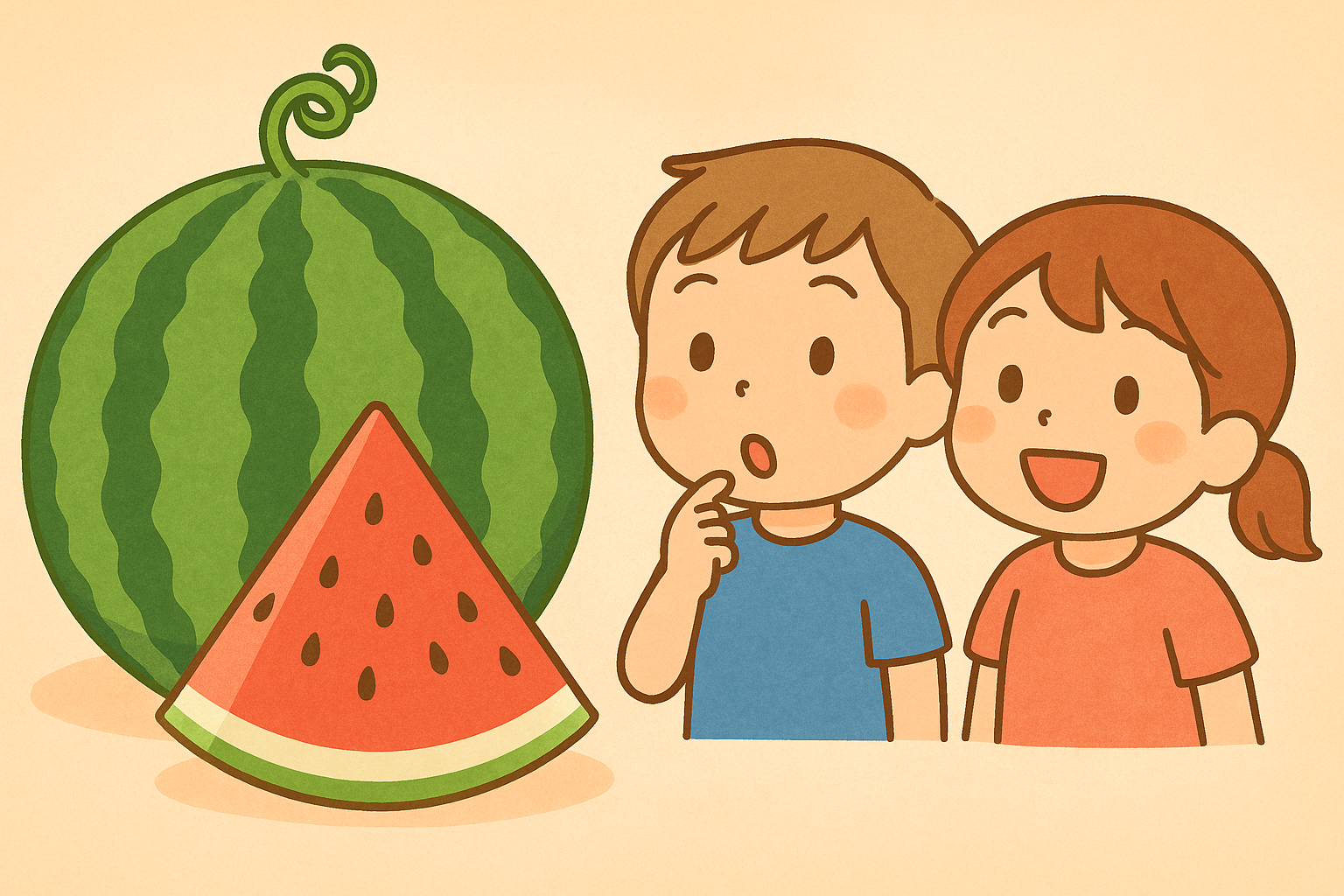
ちょっとした雑学
- スイカは果物のように食べられていますが、実は「ウリ科」の植物で、野菜に分類されることもあります。
- 海外では英語で “watermelon(ウォーターメロン)” と呼ばれ、「水のメロン」という意味です。
- スイカの種なし品種や、皮が薄くて食べやすい「小玉スイカ」も人気があります。
- 日本では「スイカ割り」など遊びの道具にもなっており、食べるだけでなく夏のレジャーにも使われています。
- 山形県や熊本県など、日本各地で高品質なスイカの栽培が盛んです。
親子で話してみませんか
「ねえ、スイカって本当は野菜だって知ってた?」
「元は外国から来たんだよ。昔の日本では、どんな風に食べられてたんだろうね?」
こんなふうに、夏の食卓に並ぶスイカを通して、食べ物の歴史や言葉の広がりに親子で触れてみるのも楽しい学びになるのではないでしょうか。

