日本語になった外来語たち#14:カキ氷 /cagueiro
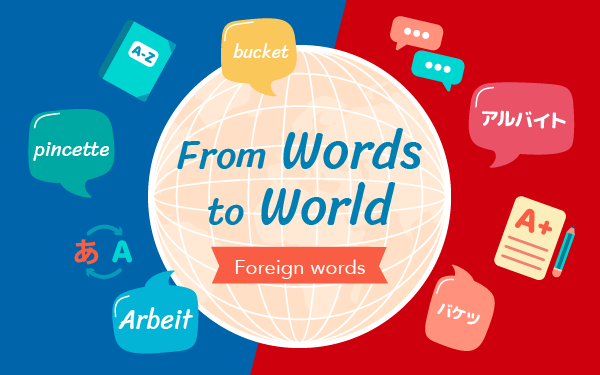
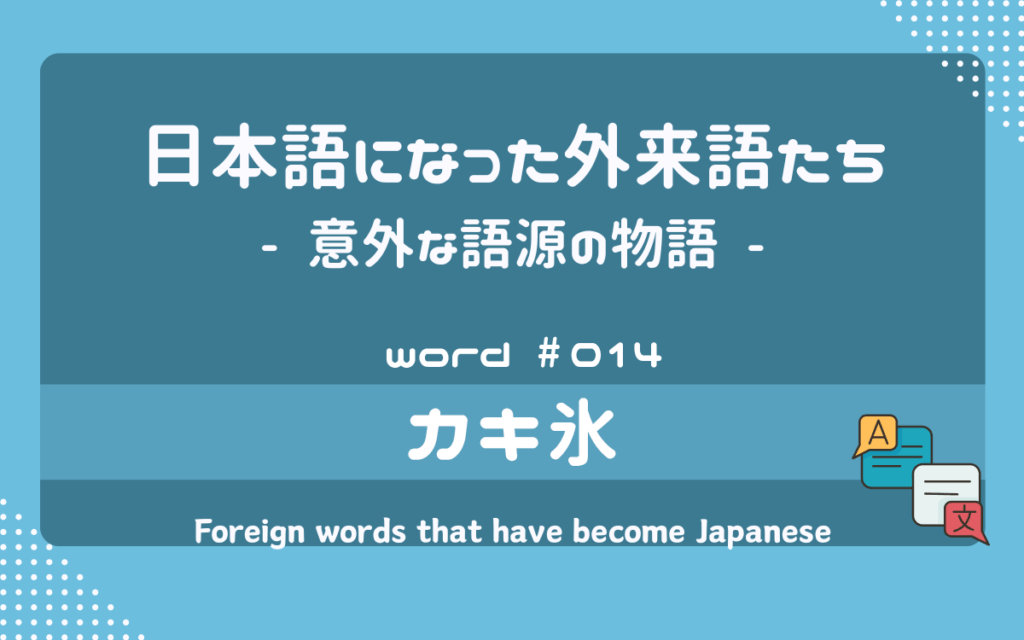
夏といえば、冷たくて甘い「カキ氷」。日本の夏祭りや海辺の店でよく見かけますが、この名前の由来やルーツを知っていますか?実は「カキ氷」という呼び方の中には、外国から伝わった言葉の要素も含まれています。
今回は、カキ氷の歴史や語源、そして日本ならではの発展について紹介します。
語源
- 言葉:カキ氷(かきごおり)
- もとの原語:ポルトガル語 cagueiro(諸説あり)
- もとの意味:氷を削ったものや氷を扱う道具
- 日本語での使われ方:削った氷にシロップやトッピングをかけた夏の冷たいおやつ
日本語として使われるようになった背景
カキ氷自体は、日本では平安時代から存在しており、『枕草子』にも「削り氷」に甘葛(あまづら)の汁をかけて食べる様子が描かれています。ただし、この頃は貴族しか口にできない貴重品でした。
江戸時代に入ると、氷室で保存した天然氷が使われるようになり、少しずつ庶民にも広まりました。明治時代には製氷技術や氷削機が海外から伝わり、より手軽に作れるようになりました。カキ氷という呼び名には、ポルトガル語由来の「カキ(削る)」説があり、日本の「氷」と組み合わさって定着したといわれています。

ちょっとした雑学
- 海外にも似たような氷菓はあり、台湾の「雪花冰(シェーファーピン)」やハワイの「シェイブアイス」が有名です。
- 日本のカキ氷は、細かく削ったふわふわ食感が特徴で、最近では氷にミルクやジュースを混ぜて凍らせるアレンジも人気です。
- ご当地カキ氷も多く、鹿児島の「白熊」や日光の天然氷を使ったカキ氷など、地域色豊かなメニューがあります。
- 英語では「shaved ice」と呼ばれますが、日本の「カキ氷」は見た目も味もより繊細で、外国人観光客にも好評です。
- 夏祭りの屋台のカキ氷機は、実は昭和からあまり形が変わっていません。
親子で話してみませんか
「昔のカキ氷ってどんな味だったのかな?」と子どもに問いかけてみましょう。
「おばあちゃんの子どもの頃は、シロップは何味が人気だったの?」と世代を超えた話を聞くのも楽しいです。
さらに、「日本のカキ氷と海外の氷のおやつ、どこが違うのか比べてみようか?」と、文化の違いを学ぶきっかけにもなります。

