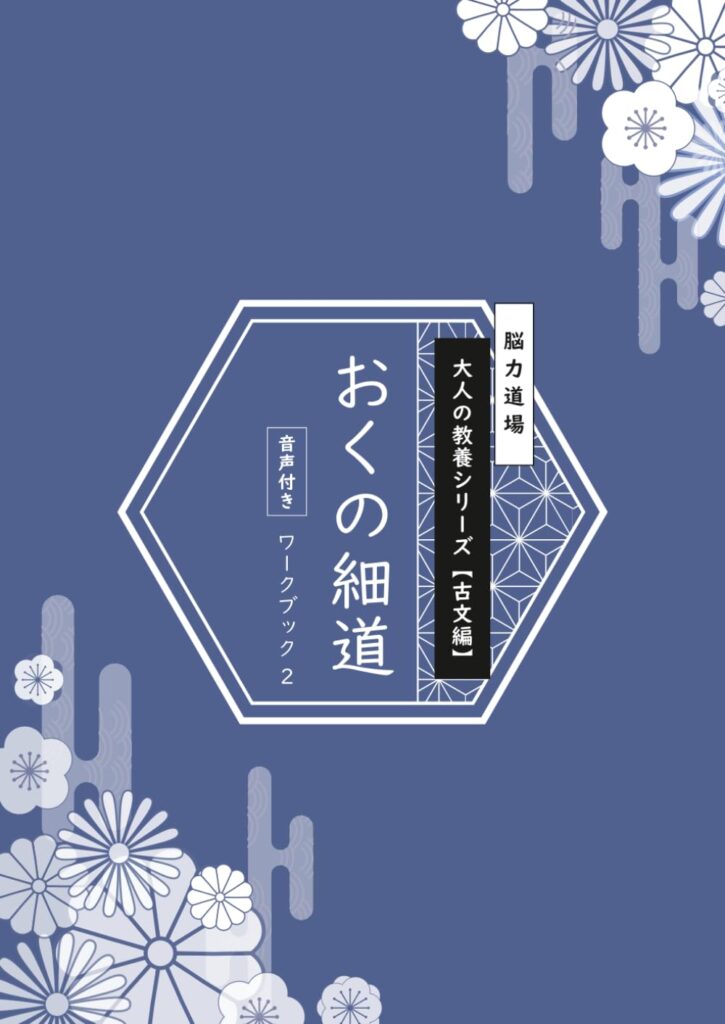第6回 諸行無常ってどういう意味?

古典原文
祇園精舎の鐘の声、
諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、
盛者必衰のことわりをあらはす。
おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。
―「平家物語」
現代語訳(小学生向け)
祇園精舎の鐘の音には、この世のすべてのものは常に変わり続けるという「無常」の響きがある。
沙羅双樹の花の白さは、どんなに栄えた者でもやがてはほろびるという道理を示している。
おごり高ぶった人も長くは続かず、それは春の夜に見た夢のようにはかない。
子ども向けの解説
『平家物語』は、今からおよそ八百年前の鎌倉時代に作られたといわれる物語です。
平安時代の最後におこった、平氏と源氏という二つの大きな武士団の戦いをえがいた物語です。平氏が一度は戦いに勝利し、天下を手に入れ、豪華なくらしをしていましたが、のちに一度は平氏に敗れた、源頼朝をリーダーとする源氏にほろぼされるまでがえがかれています。
平氏はいったん勝って国の中心をにぎりますが、のちに源頼朝を中心とする源氏にやぶれてしまいました。
この冒頭の文には、難しい四字熟語がいくつも出てきます。
「祇園精舎」はインドにあるお寺の名前で、「沙羅双樹」は仏教をひらいたお釈迦さまが亡くなったとき、そばにあった木のことです。
「諸行無常」とは、「すべてのものは変わっていき、永遠に同じままではない」という意味です。
また「盛者必衰」とは、「どんなに強く栄えた者も、いつかは力を失ってしまう」という意味です。
この諸行無常と盛者必衰という二つの言葉は『平家物語』全体に通じる大切な考え方です。
天下を手にしたほど強かった平氏も、永遠にはその勢いは続かず、やがてほろびてしまいました。
このお話を通して、「どんなものもずっと続くわけではない」「命ははかないものだ」という思いが、人々に伝わっていったのです。

親世代・祖父母世代向けの解説

平家物語は鎌倉時代中期に成立したと言われる軍紀物語です。清盛が政治の頂点に立つまでの栄光、そして源頼朝・義経ら源氏との戦いによる滅亡へと物語は展開していきます。物語は勝者である源氏よりむしろ、滅びる側の平氏に対する哀れみを中心に語られます。作者は不詳ですが、琵琶法師が琵琶をひきながら物語を語り伝えたことで、多くの人に広まりました。物語の冒頭にある文章には無常観が表現されています。無常観とは仏教の思想で、全てのもの(諸行)は、永遠には続かない、移り変わる(無常)という意味です。
諸行無常、盛者必衰という難しい熟語も登場しますが、声に出して読んでみると意外と音読しやすく、この熟語が心地よいリズムとして感じられます。それは、この平家物語が琵琶法師による弾き語りとして、口頭で人々に伝わってきたからでしょう。 平家物語の序文だけでなく、本文にも四字熟語が使われていることがわかります。四字熟語には意味だけでなく、言葉として口に出してみると唱えやすい、格好いい響きをもつものがあります。
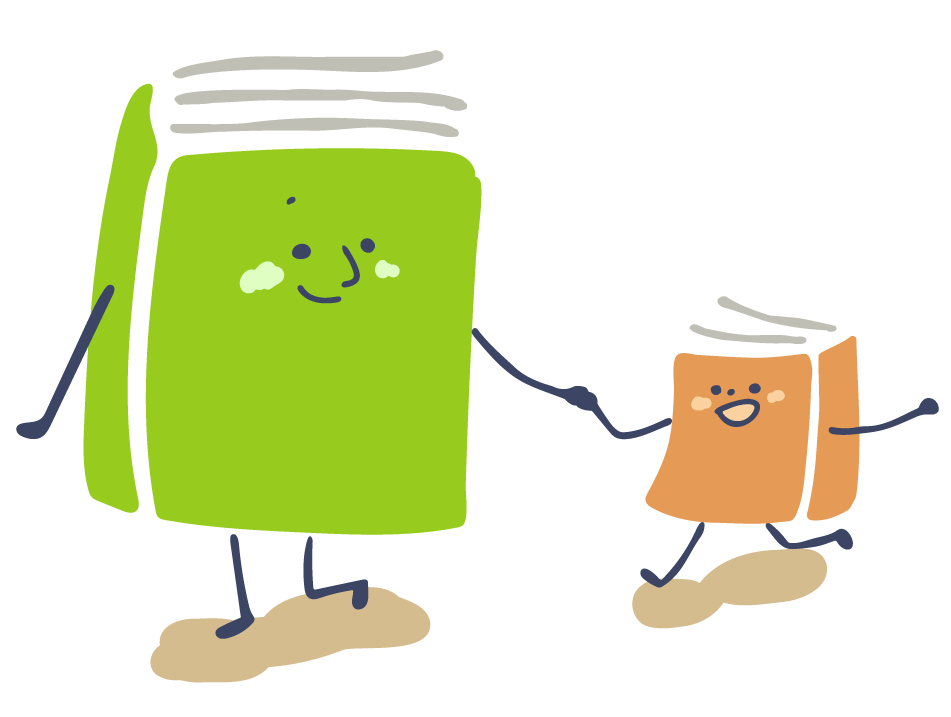
どんな四字熟語の意味が好きか、または格好がいいか、話しあってみるのも面白いですね。無常観についても、「ずっと続くものはないね」と思える事柄が身の回りやこれまでの経験でなかったか、話しあってみるのもいいですね。
\ お知らせ /
「脳力道場 大人の教養シリーズ【古文編】奥の細道・その二」を、その一に引き続き出版いたしました!音声による聞き取り・音読トレーニングを取り入れた、古文の学び直しとともに、ワーキングメモリーのトレーニングも行うことができる画期的な脳トレ教材です!
今回扱った平家物語のように、文章を声に出して読む、聞くことは脳の活性に大きな効果をもたらします。 ぜひ、こちらも音読を通して脳のトレーニングとしてお役立てください!
記事作成者
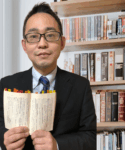
長尾 一毅 (ながお かずき)
15年以上にわたり小・中・高校生の国語指導を担当。読解力こそ全教科の基盤と考え、集団授業から個別家庭教師まで多様な教え方を実践し、生徒の理解度に応じた指導を行う。脳科学の知見を交えた問いかけと対話を重ねることで、「自分で考え抜き、答えを導き出す」習慣を育む指導に定評がある。