
第5回 日本最古の物語、どれほど古いの?

古典原文
今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。
野山にまじりて竹をとりつつ、よろづのことに使ひけり。
―「竹取物語」
現代語訳(小学生向け)
今となっては昔のことだが、竹取のおじいさんという者がいた。
野山に分け入って竹を取っては、いろいろなことに使っていた。
子ども向けの解説
竹取物語は、日本で一番古いと言われる物語です。今から千年前、平安時代に書かれたものと考えられていますが、作者はわかっていません。「かぐや姫」という名前の昔話として多くの人に親しまれていますね。
昔話として他に思い浮かぶのは「桃太郎」「金太郎」「浦島太郎」「鶴の恩返し」などですが、これらは「かぐや姫」ができた時代とは全く違います。桃太郎たちは室町時代の終わりから江戸時代、約五百年から四百年前の話だとされています。そのため「かぐや姫」はこれらより倍も昔にできた物語ということが分かります。
「今は昔」は「今となってはもう昔のことだが」という意味で、今の「むかしむかし、あるところに」にあたる昔話の決まり文句です。今とは少し言い方が違いますね。
言葉づかいにも違いがあり、「あった」「いた」は「ありけり」、「使っていた」は「使いけり」と古い言い回しが使われます。このように昔の事を表すとき、今では「た」という言葉を主に使いますが、昔は「けり」という言葉を使っていました。 また、昔は、「さまざまなもの」という意味で、「よろづ」という言葉を使っていました。漢字で書くと「万」、今でも「万屋」と書いて「よろづや」と読むことを知っている人もいるかもしれませんね。

親世代・祖父母世代向けの解説

竹取物語は平安時代前期に成立した、日本最古の物語であり「物語の出で来はじめの祖」と称されます。作者は不詳です。室町時代から成立した『御伽草子』よりも、さらに昔に生まれた作品なのですね。
冒頭の「今は昔」という表現も、今の「むかしむかし」と異なります。一般的な訳は「今となっては昔のことだが」ですが、「昔、何々という人が、何々をした、ということが今では語り伝えられている」と解釈する説もあります。
また、この冒頭の文の続きには係り結びなどの古文独特の表現が用いられています。「好きこそものの上手なれ」ということわざは、この古文の係り結びの表現が今にも残っている例といえます。
今でもことわざや慣用句、童謡などの中にも、こうした昔の言葉や表現がたくさん生きている例があります。
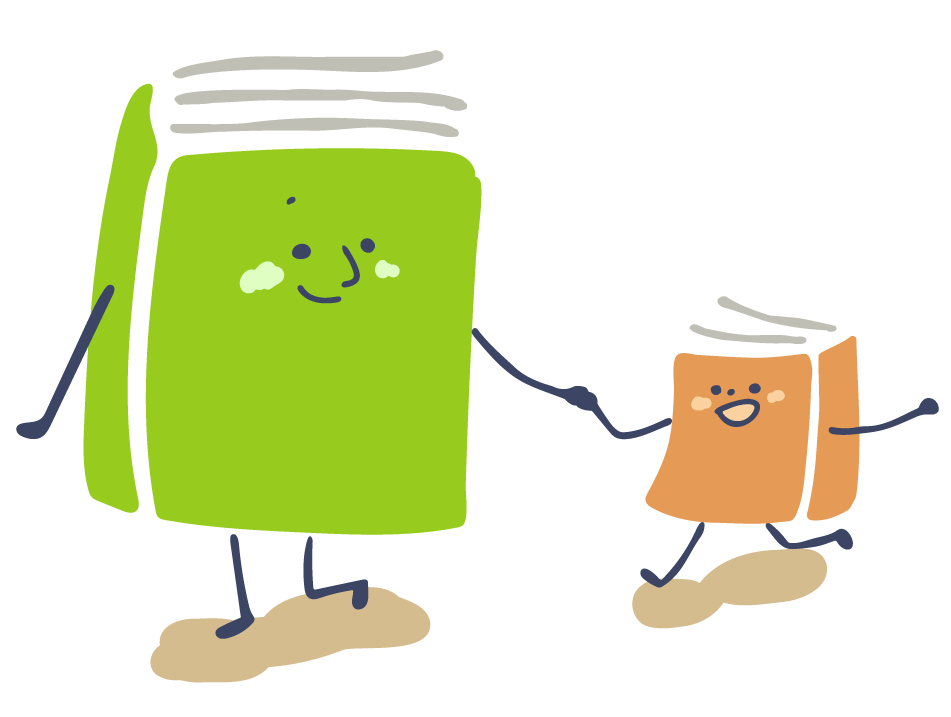
「このことわざ、どんな意味かな?」「おじいちゃんおばあちゃんは知ってる?」と、親子や家族みんなでワイワイ話してみると、新しい発見やびっくりがあるかもしれませんね。
記事作成者
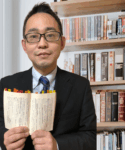
長尾 一毅 (ながお かずき)
15年以上にわたり小・中・高校生の国語指導を担当。読解力こそ全教科の基盤と考え、集団授業から個別家庭教師まで多様な教え方を実践し、生徒の理解度に応じた指導を行う。脳科学の知見を交えた問いかけと対話を重ねることで、「自分で考え抜き、答えを導き出す」習慣を育む指導に定評がある。
