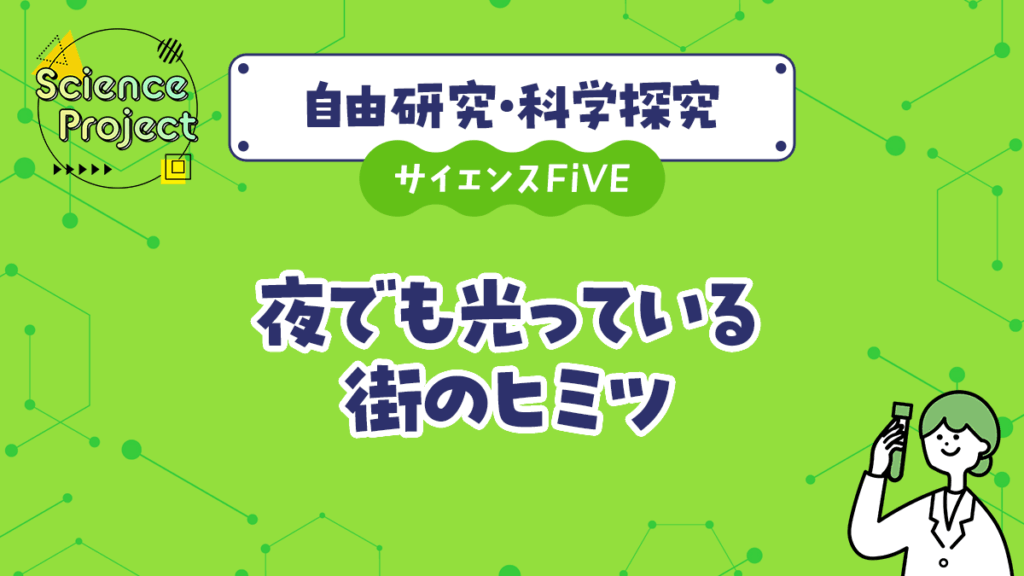
夜でも光っている街のヒミツ

夕方になって日が沈んでも、私たちが暮らす街は完全に暗くなることはありません。
道路の上には街灯が光り、建物の窓からも明かりがもれています。
自動販売機、コンビニ、看板のライトまで、「夜の街」は思ったよりも明るいものです。
でも、その“あたりまえの明るさ”が、自然にどんな影響を与えているか、考えたことはありますか?
今回は、身近にある「光」から、自然環境や生き物の世界に目を向けます。
夜の光が与える影響
もともと、夜は暗いのが自然の姿です。月明かりや星の光だけで照らされていた時代には、動物や虫、人間も「昼は活動して夜は休む」というリズムを守って生きていました。

ところが、人工の光、つまり「人工照明(じんこうしょうめい)」が使われるようになると、夜でも明るい場所がどんどん増えていきました。とくにLEDの光は、少ない電力でとても明るく光るため、近年では街灯にもたくさん使われています。
こうした「光のある夜」が人間には便利でも、生き物たちにとっては“まぶしすぎる夜”になっているのです。
「光害(ひかりがい)」とは
明るい街は、人間にとっては安全で暮らしやすくなる一方で、いろいろな課題も見つかってきました。
たとえば、夜行性の虫たちは、街灯の光に集まってきてしまい、本来の生息地に帰れずに命を落とすこともあります。また、海では、砂浜でふ化したウミガメの赤ちゃんが、月の光ではなく、人工の光の方に向かってしまい、海へたどり着けなくなることも報告されています。また、人工の強い光によって、動物の睡眠や移動のリズム、人間の体内時計にも悪影響をおよぼすことがあるといわれています。

「光害(ひかりがい)」という言葉を聞いたことがありますか?
これは、必要以上の光が周囲の自然や健康に悪い影響を与えることを意味します。
解決に向けた取り組みの事例
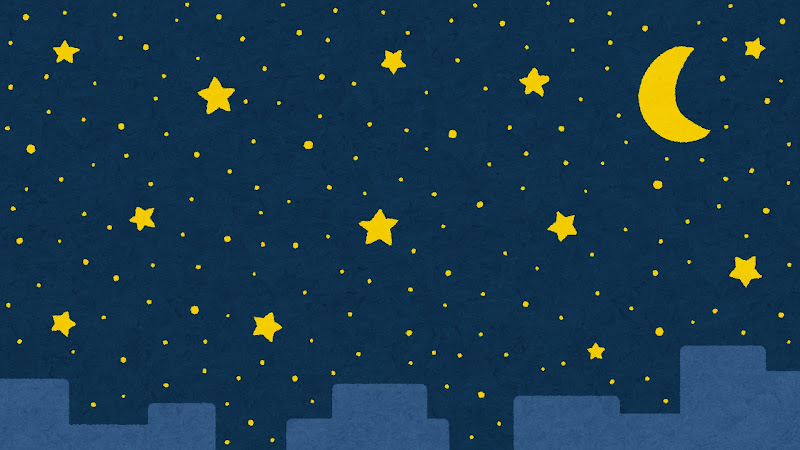
最近では、日本でも「生き物にやさしい街灯」を使おうという動きがはじまっています。たとえば、ある地方のまちでは、虫が反応しにくい波長のLEDを使った街灯を設置したり、夜10時以降は明るさを自動でおさえるしくみを導入したりしています。
さらに、光害をへらすために「星空保護条例」を定めて、夜の明るさをできるだけおさえ、星が見える静かな夜空を守ろうとする地域も出てきました。
このように、「便利だから使う」から「環境にも配慮して使う」へと、街の明るさも“やさしい光”に進化し始めているのです。
みなさんならどうする?

あなたの家のまわりや通学路には、どんな光がありますか?
夜、自分の目で確かめて、「明るすぎるかな?」「どこまで光が広がっているかな?」と感じたことを書き出してみましょう。 また、みなさんの部屋のあかりは寝る前までつけっぱなしですか?
夜の時間にどんなふうに光を使っているか、家族で話し合って工夫できることを考えてみることをおすすめします。
