日本語になった外来語たち#09:レジャー/ loisir・leisure
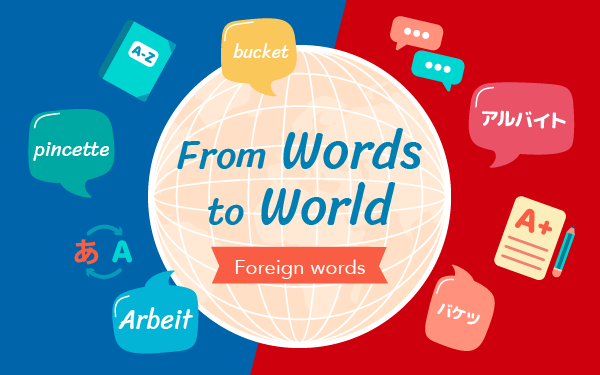
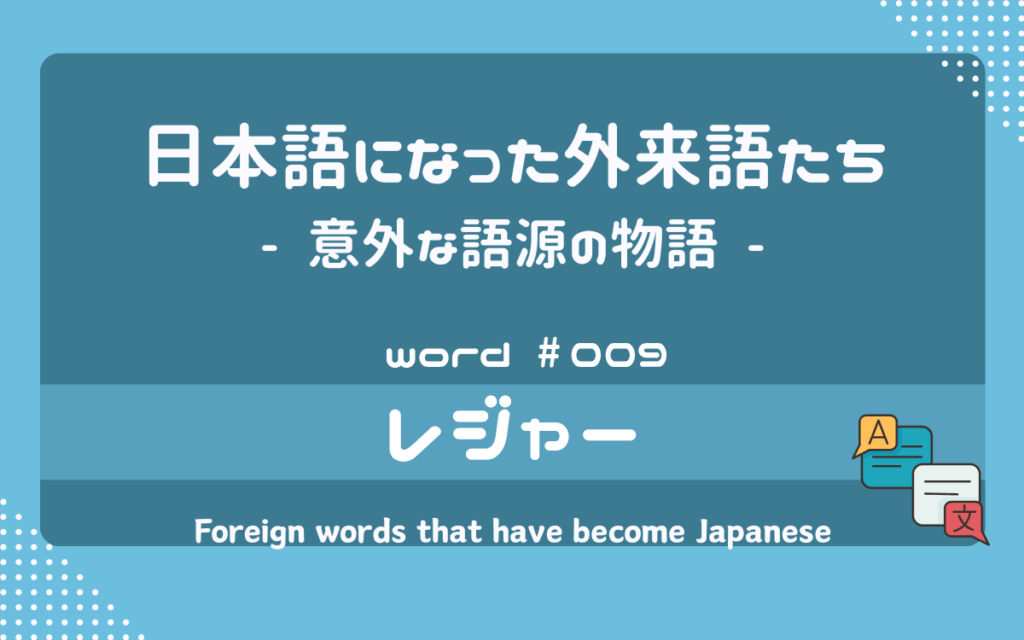
「レジャー施設」「レジャーシート」など、私たちの周りには「レジャー」という言葉がたくさんありますよね。でも、この言葉の本来の意味は、日本で使われている意味とは少し違うんです。
今回は「レジャー」という言葉の語源や歴史、日本での使われ方について見てみましょう。
語源
- 言葉:loisir(ロワジール)→ leisure(レジャー)
- もとの原語:フランス語(loisir)、英語(leisure)
- もとの意味:自由な時間、余暇
- 日本語での使われ方:遊びや行楽など、休日にする特別な楽しみ・活動を指す
日本語として使われるようになった背景
「レジャー」という言葉は、もともとフランス語の「loisir(自由時間)」が語源で、それが英語の「leisure(余暇)」として使われるようになりました。
日本では戦後、生活にゆとりが生まれると同時に「休日の楽しみ」や「家族での娯楽活動」を表す言葉として「レジャー」が広まっていきました。
英語圏では「leisure」は単に「自由な時間」を意味するのに対して、日本では「レジャー=特別な楽しみのための活動」として、やや“イベント的な意味”で使われることが多いのが特徴です。
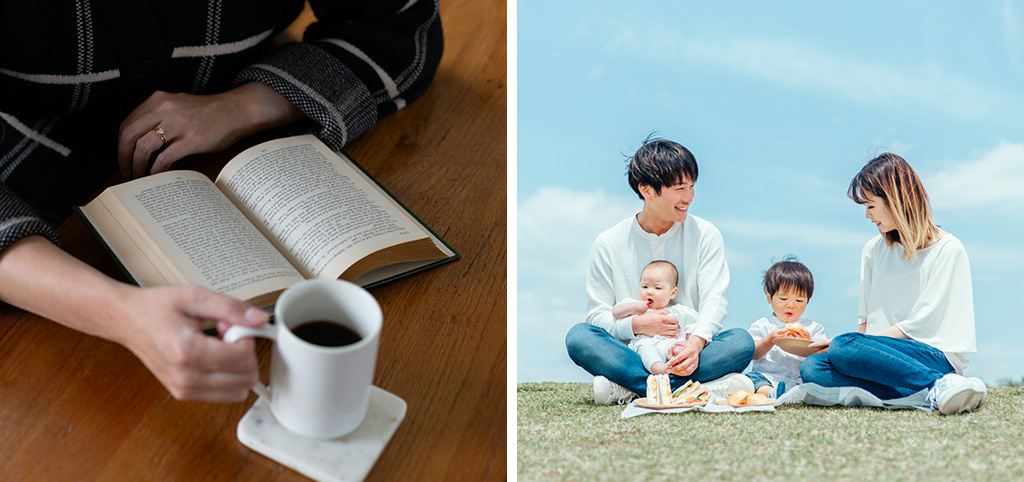
ちょっとした雑学
- 日本では「レジャー施設」「レジャー産業」など、観光や娯楽に結びついた表現が多く使われます。
- 英語では「レジャーシート(敷物)」のような表現はなく、「picnic blanket」などが一般的です。
- 「レジャー白書」という年次統計もあり、日本人の余暇活動の傾向がデータとしてまとめられています。
- 近年は「インドアレジャー(ゲーム、動画視聴など)」や「プチレジャー(近場のお出かけ)」という新しい形も増加中。
- 本来の意味に立ち返ると、「ぼーっとすること」も立派なレジャーなのですね!
親子で話してみませんか
「『レジャー』って聞くと、どんなことを思い浮かべる? 実はこの言葉、もともとは『自由な時間』って意味だったんだって。遠くへ出かけなくても、おうちで好きなことをする時間もレジャーなんだよ。今度のお休み、どんなレジャーをしてみたい?」

