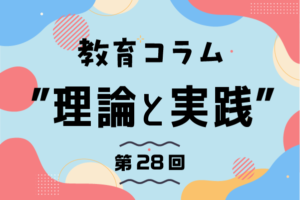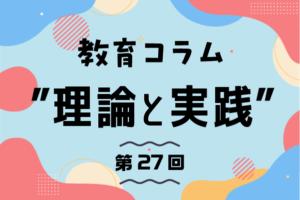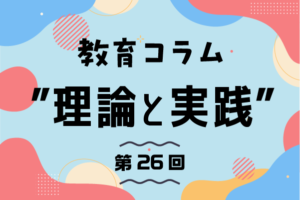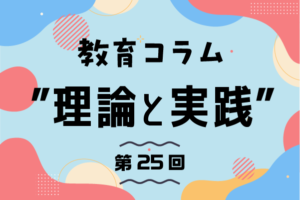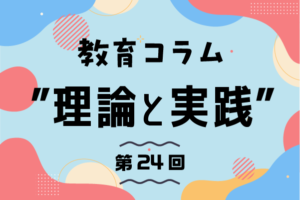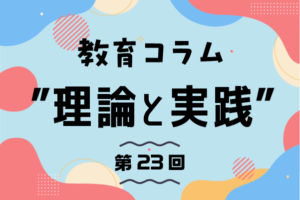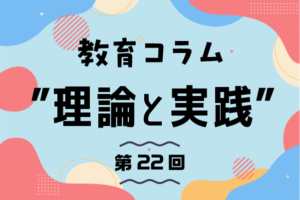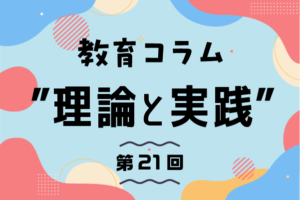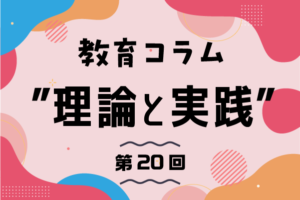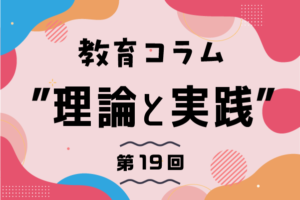第28回 学習は「入力」と「出力」の繰り返し|教育コラム “理論と実践”
学習は「入力」と「出力」の繰り返し 養老孟司先生による講演『現代人がおろそかにしている勉強・学習―これからの時代に必要な「学び」とは?』の動画をぜひご覧ください。 止まっている物に歩きながら近づくと、物が大きく見えますが […]
第27回 読解には知識が不可欠|教育コラム “理論と実践”
読解には知識が不可欠 参考文献:『教師の勝算』(東洋館出版社 Daniel T. Willingham著) 背景知識は、他の人が話していることや書いたことを理解するための助けになります。背景を知らないと、十分な理解ができ […]
第26回 語彙力の捉え方|教育コラム “理論と実践”
語彙力の捉え方 こどもの読解力を高めるには、「語彙力」と「ワーキングメモリ」がカギとなります。「語彙力がカギ」とは「語彙の量を増やす」だけではありません。 「語彙力」を以下の4つに分類して捉えることが大切です。 これらの […]
第25回 人が最も効率よく学習できる三条件 -ミネルバ大学から-|教育コラム “理論と実践”
人が最も効率よく学習できる三条件 -ミネルバ大学から- サンフランシスコに拠点を置き、「21世紀最初のエリート大学」として設立されたミネルバ大学(Minerva Schools at KGI)は、以下の特徴があります。 […]
第24回 教科書に出てくる「語数」|教育コラム “理論と実践”
教科書に出てくる「語数」 『国語教師のための語彙指導入門』(鈴木一史著 明治図書)は、子どもたちの語彙力について、データに基づいて定量的に分析がされています。 第一章の「言葉と語彙」には、小学校1年生から高校1年生のすべ […]
第23回 こどもの「手書き離れ」|教育コラム “理論と実践”
こどもの「手書き離れ」 こどもたちの文字が薄いために、小学校で鉛筆の濃さの指定をHBから2Bに上げる動きが広がっているようです。 AERA dot (2021年6月7日号の記事)には、「『正しいものに〇をつけましょう』と […]
第22回 「意味調べ」の意味|教育コラム “理論と実践”
「意味調べ」の意味 こどものみならず、私たち大人も日常的に「意味調べ」をしています。 しかし、大人のそれは、辞書を使っての「意味調べ」とは異なり、Yahoo!やGoogleの「検索キーワード」を使い、短時間で「答え」にた […]
第21回 分散型の練習|教育コラム “理論と実践”
分散型の練習 『教育効果を可視化する学習科学(ジョン・ハッティ、グレゴリー・イエーツ著)』によると 数日から数週間をかけて短く切って学習することは、ある程度の時間をかけて一度に学習するより効果が高く、この分散型の練習は、 […]
第20回 学力に影響を与える家庭要因|教育コラム “理論と実践”
学力に影響を与える家庭要因 『教育の効果-メタ分析による学力に影響を与える要因の効果の可視化-(図書文化)ジョン・ハッティ著』は、膨大な量の論文を整理してまとめられています。 この本のページ数は422ページに及ぶため、今 […]
第19回 読解力を高めるためにワーキングメモリのトレーニングを|教育コラム “理論と実践”
読解力を高めるためにワーキングメモリのトレーニングを 「ワーキングメモリ」が学びの鍵になること、そして、ワーキングメモリと読解力が深く関係することは脳科学的に広く知られています。 読解は、記憶として脳内にある言葉・語彙を […]